自然と学力が伸びる勉強習慣を【3ステップ】で身につける
- 高石 司(ライブラ代表)
- 2022年8月12日
- 読了時間: 9分
更新日:2024年4月22日

こんにちは。
当ブログでは、主に中学生や高校生を対象とした日常の勉強活動や学校生活に役立つ情報をご案内しております。
本日のテーマ
学力が伸びる勉強習慣の作り方を3ステップで紹介
INDEX
◆ 前書き
◆ まとめ
記事作成者について

大学受験専門の個別指導塾
ライブラ京橋校担当|高石 司
関西大学(社会学部 メディア専攻)卒
関西の大手進学塾にて新卒1年目より新規開校校舎長を担当し、(当時)全54校中1位の校舎成長率を達成。新人講師採用職・エリア統括職等を経て2018年退職、翌年にライブラ京橋校を設立。
塾外での正しい勉強習慣を定着させる「楽して学力を上げる学習指導」をモットーとし、のべ2000名以上の学習相談・進路面談を担当。関関同立・産近甲龍を中心に、毎年多くの合格者を輩出している。
前書き
本記事は、勉強習慣で悩みを抱える生徒の多くに共通した【学力を自然と伸ばす心得】について3ステップ形式で紹介します。
せっかく自力で勉強計画を立ててみたものの、思うように成績が伸びず次第にモチベーションも下がってしまい、結局勉強するのを止めてしまったという声は後を絶ちません。
一方、スマホやテレビゲームの多くは非常に面白くて、どんなにプレイしても飽きずにどんどん進められるという方もたくさんいるでしょう。
これは名作ゲームの多くにおいて、プレイする中でプレイヤー自身がグングン上達しているのが実感できるように極めて綿密にバランス設計されているからです。
翻って、学校の授業や受験勉強は一般的にそのように作られていませんので、自分自身で成長を実感できるように工夫する必要があります。
結局のところ、皆さんのやる気は、皆さん自身で上げるしかないのです。
今回も最後までお付き合いください。
① 【意識編】主体的意識を持つ
勉強やスポーツを含むあらゆる能力開発の場面で昔から語られている「古くさい言い回し」ではありますが、やはりそれだけ重要なポイントです。
「ただ学校に通い続けているだけで勉強スキルがみるみる上達する」のであれば、日本中の学生がこんなにも受験勉強に苦心することはないはずです。
とはいえ、特に学校のような集団授業の受講時間の大半は、必然的に「講師のお話を静かに座って聞く」ことになります。
このような「視覚及び聴覚刺激をただ漫然と受容する」という状況に長時間置かれると、私たちの脳は"省エネモード"に移行します。
その結果、耳から入ってくる情報の大部分をたとえ授業中に居眠りなどしていなくても「ただの環境音」と同じようにスルーしてしまうことにつながるのです。
入試直前期を迎えるころには必死で頭に叩き込むことになる各分野の基本事項や公式が、校庭から聞こえてくる小鳥のさえずりと等しく情報処理されてしまうということです。恐ろしいですね。
工夫①:"動画視聴"ではなく"ライブ参加"を!!
たとえば、壇上の先生と目があったら「これはきっと私へのファンサだ!!」と思って積極的に頷いてみましょう。先生もきっと喜びます。
また、授業中の先生の何気ない独り言や自分語り、あるいはふとした問いかけに対して心の中で「ツッコミ」を入れてあげましょう。容赦ないキレキレのやつでも構いません。
「集団授業=一歩通行のコミュニケーション」であると考えている方も多いですが、私はそうは思いません。
集団授業の学習効果を最大限に享受するためには、受講者側の主体的な参加意識が間違いなく必須であり、これは上記のような「心がけ一つ」ですぐに改善できます。
心がけに加えてもう一つオススメのアクションは、授業中に先生が話していた「板書外の情報やコメント」をノートにメモとして追記しておくことです。
たとえ受講するのが映像授業だとしても、上記と同様のイメージを心がけて授業に参加してみてください。
そして1週間後にノートを見返して、当時の授業の内容を思い出そうとしてみてください。これまで見えていた復習の解像度が、色が、全く異なって感じられるはずです。
② 【計画編】ステージのクリア条件を明確にする
スマホゲーム等を面白いと感じる理由について、先ほど紹介した「プレイヤー自身が成長を実感しやすい」という要素に加えて「ゲーム内で得られる報酬が魅力的である」という点も大きいです。
ポケモンだとジムリーダーを倒したらもらえるバッジなんかが象徴的ですね。
少々話がそれましたが、ここで重要なポイントは魅力的な報酬をゲットするための「クリア条件」が明確であるという点です。
ポケモンであればジムリーダーと戦って、相手の手持ちポケモンを全て倒せば報酬(バッジ)が得られるわけです。
さて、皆さんにとっての「勉強によって得られる報酬」とはなんでしょうか?
第一志望校の合格?それとも学年順位の維持?
では「その報酬を得るためにクリアすべき条件」とは、一体なんでしょうか?
これらの点を具体的に言語化しないまま、最終的な報酬だけを得ようとするから、多くの受験生が四苦八苦しているわけです。
工夫②:勉強はクリア条件を突破するための"レベル上げ"!!
ジムリーダーに勝てない時は、近くの草むらでタイプ相性の良いポケモンを捕まえたり、手持ちポケモンのレベル上げをしたり、新しい技を覚えさせたりします。勉強も同様です。
〇〇大学合格という報酬を目指すなら「志望校の初見の過去問で合格最低点を突破すること」がこのゲームのクリア条件であり、そのために必要なあらゆる対策や工夫を凝らすことこそ、皆さんにとっての受験勉強そのものなのです。
現状の学年順位の維持についても同様ですが、こちらは「その報酬が自分にとって本当に魅力的かどうか」をきちんと考える必要があります(その順位でほんまにええんか...?)
いま目の前にある授業、課題という「レベル上げ作業」の先に、果たしてどんな技が習得できるようになるのか、可能な限り言語化した上で授業に臨みましょう。
たとえば数学で「黄チャートの例題水準の演習が楽々解けるようになる」という技が身につけられれば、中堅程度の私立大過去問であれば十分挑戦できるレベルになります。
英語であれば「英文法スクランブル第1章の文法問題を全て即答できるようになる」が習得できれば、関関同立入試水準の英文法知識としては十分です。
学習目標(クリア条件)の言語化を習慣づけることで、この先の人生の様々なシーンにおいて「新しいことを身につけるのが上手い人」に近づけます。
私自身、受験勉強を通じて得られる「将来役立つスキル」とは身につけた知識そのものではなく「変化し続ける社会にリアルタイムで対応できる学習力と自己管理スキル」だと考えています。
受験勉強は、将来皆さんが社会をサバイバルするための体力づくりです。
③ 【行動編】"忘れないようにする"より大事なこと
突然ですが、受験生当時の私はその日はじめて勉強した内容のうち「まぁ半分くらいは翌日には忘れてるだろうなぁ」ということを前提に年間学習計画を立てていました。(かの有名な"エビングハウスの忘却曲線"の存在を知ったのは、大学進学後に心理学関連の講義を受講してから)
実際、相当多くの人たちにも当てはまる学習&忘却ペースだと思っていますので、上記の学習スタンスは個人的にとてもおすすめです。
大事なのは忘れないことを極度に意識するのではなく、忘れたということを正しく認識して復習する算段を立てておくことです。
しかし全ての科目を「画一的に」「暗記ベースで」習得しようとするのは、当然ながら学習のコストパフォーマンスを著しく低下させることにつながります。
たとえば数学のメジャーな勉強方法の一つに「解法暗記」という学習方法があります。
解き終えた様々な演習問題の「単元別の解き方」を暗記することで、素早く・正確に解答に辿り着こうとするテクニックですね。
確かに解法暗記はオススメの学習法の一つですが、なかには「解法暗記してるけど、肝心の初見問題に対応できない!」と嘆く受験生も少なくありません。
工夫③:テスト時における"再現性"を意識しよう
解法暗記の精度が不十分である可能性も捨てきれませんが、悩みを抱える受験生の多くに共通する特徴として「解説冊子がとてもきれいなままである」という点が見られます。
なかには「ほぼ丸つけにしか使ってないようなきれいさ」の冊子も。
特に数学をはじめとした理系科目や英文法といった論理性を要求される分野においては、「解説冊子にあるロジックを頭の中に再構築し、自分の言葉で説明できるようになる」という学習アプローチが非常に効果的です。
そもそも解法暗記とは、解説内容の文を一字一句暗記する学習法ではありません。
解説冊子の内容の行間をきちんと読み取った上で、たとえば一学年下の後輩に「自分の言葉で解法を説明できるかどうか」という観点から学習内容のアウトプットを試みましょう。
「いやいや、そんなことができるなら受験生じゃなくてむしろ先生レベルじゃん!」と思った方もいるかもしれませんが、ご安心ください。
皆さんの先生はもっともっと遙かに高い次元での単元理解に基づいて解説の際に用いる言葉を慎重に選びながら万全を期して授業を行なっています。皆さんが"先生"と肩を並べるにはもう少し練度が必要です。
お一人で復習を行う際は、皆さんの頭の中に「ちょっとアホな後輩」を作り出して、解説冊子の内容をじっくり読み解きながら、自分の言葉で彼にレクチャーしてみてください。
これは私個人の持論であり、実際の指導経験ですが解説冊子がきれいなままの受験生は文系理系問わず「ある一定の学力以上には伸びません」。
まとめ
以上、学力が伸びる勉強習慣の作り方を3ステップで紹介させていただきました。
ゲームやスポーツ全般においても言えることですが、ずっと上達(変化)しないままだと、すぐに飽きてしまうのが人間というものです。
日々の勉強を飽きることなく継続するためには、変化や自身の成長に対して常に敏感でなくてはいけません。誰かが教えてくれる環境ならまだしも、多くの場合自力で言語化する必要があるからです。
受験勉強に限らず、日々の学校授業や復習にも応用できる考え方についてもお伝えしましたので、どれか1つでも活かせそうなものがあれば幸いです。
▶︎ 第一志望に現役合格したいが、何からすればいいか分からない
▶︎ 大学に進みたいと思ってはいるが、なかなか目標が定まらない
▶︎ 部活やアルバイトで忙しいので、なるべく勉強効率を高めたい
上記のような悩みをお持ちの方は、お気軽に当塾(ライブラ京橋校)までお声掛けください!
当ブログの中の人が、皆さんの日々の勉強の最適化をお手伝いします。
またYouTubeチャンネルを開設していますので、本記事が面白かったという方は是非ご覧ください!
今回も最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

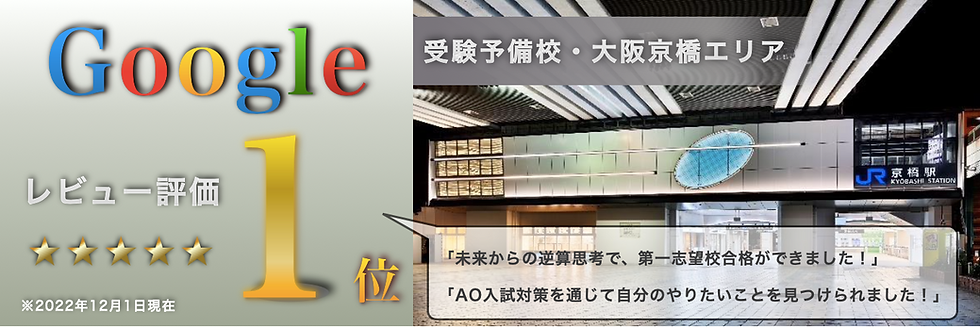

Comments